循環器内科とは
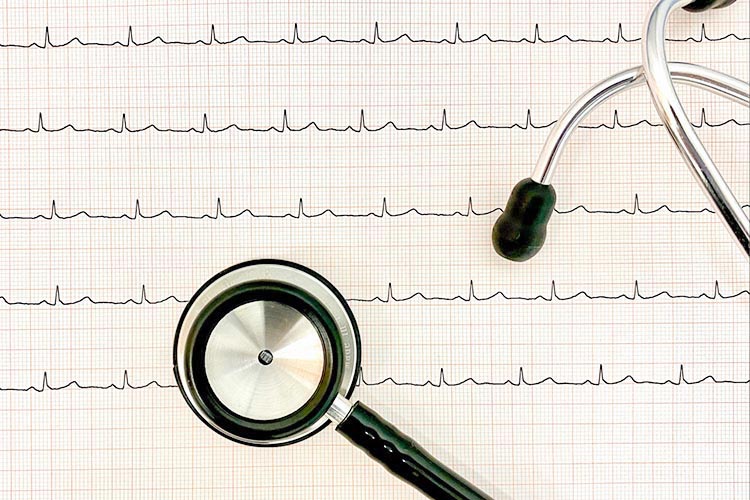
循環器とは、血液やリンパ液などの体液を、体内で循環させるための器官(心臓、血管(動脈、静脈、毛細血管)、リンパ管)の総称です。循環器内科では、これらでみられる症状や病気について、薬物療法を中心とした治療を行います。
よくみられる症状としては、動悸・息切れ、むくみ、胸痛、めまい、ふらつきなどが挙げられます。このような症状に心当たりがある方は、一度当院をご受診ください。診察時に医師が必要と判断すれば、X線撮影、心臓超音波検査、心電図などの検査を行い、診断をつけていきます。その結果、入院加療や高度医療機器による検査や治療が必要と判断された場合は、当院と連携している総合病院や専門の医療機関をご紹介いたします。
また、当診療科は英語にも対応可能です。
このような症状はご相談ください
- 胸が痛んだり、締めつけられたりする
- 少し動いただけでも息切れがする
- 動悸がする
- 脈が乱れる
- 手足や顔がむくむ
- 血圧が高い
- 失神した
- 皮膚や粘膜が青紫色になっている(チアノーゼ)
- 健診などで心電図異常を指摘された
- 胸部X線写真で異常を指摘された
- など
循環器内科で取り扱う主な疾患
狭心症
狭心症とは
狭心症とは、冠動脈(心筋に酸素などの栄養素を送り込む血管)が何らかの原因によって狭窄し、それによって心筋に十分な血液が送られなくなる状態です。胸痛(締め付けられるような胸の痛み)や圧迫感といった発作的な症状がみられるほか、嘔吐・吐き気、息苦しさを訴えられることもあります。ただ、これらの症状は15分程度で治まることが多いです。
冠動脈が狭窄する原因の大半は、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症 等)の発症によって促進される動脈硬化です。
また、種類としては、労作性狭心症、不安定狭心症、冠攣縮性狭心症の3種類に分類されます。労作性狭心症では、運動時に胸痛や胸の圧迫感などの症状がみられますが、安静にしていると治まることが多いです。不安定狭心症は、動作時でなくとも胸痛などの症状が現れるタイプです。この場合は酸素の必要量に関係なく、常に心筋が酸欠状態になっています。冠攣縮性狭心症では、器質的(臓器そのものに何らかの異常が発生している状態)な狭窄はみられませんが、冠動脈に痙攣が起こることで一時的に血流が悪化するなどして、胸痛などの症状がみられます。
検査について
心電図や運動負荷心電図の検査によって異常の有無を調べるほか、心臓超音波検査で心臓の状態などを確認していきます。また、動脈硬化の促進による冠動脈の狭窄が考えられる場合は、血液検査によって生活習慣病罹患の有無についても確認していきます。
治療について
治療の基本は薬物療法となります。この場合、症状を軽減させるβ遮断薬、血液をサラサラにする抗血小板薬、動脈硬化を予防するためのスタチン系薬剤などを使用していきます。それだけでは改善が困難と判断される場合、カテーテル治療(経皮的冠動脈形成術:PCI)を併せて行います。また、3つある冠動脈すべてが狭窄している場合は、手術療法として冠動脈バイパス手術が選択されます。
心筋梗塞
心筋梗塞とは
心筋梗塞は、血管が狭窄し、血栓で覆われることで、その先に血液が全く行き渡らなくなり、それらの部位の心筋が壊死してしまう状態を指します。なお、狭心症と心筋梗塞は2つ併せて虚血性心疾患と呼ばれることもあります。
特に注意しなくてはならないのが、重症化すると生命に影響することもある急性心筋梗塞です。強い胸痛、冷や汗、嘔吐・吐き気、呼吸困難、放散痛(左肩や上腕などで起こる)などがみられます。ただし、高齢の方や糖尿病性神経障害を発症している方は、強い胸痛を感じないこともあります(無痛性心筋梗塞)。
発症の原因は、狭心症と同様に、生活習慣病の罹患や喫煙による動脈硬化の進行がきっかけとなることが大半です。
検査について
心筋梗塞の場合、患者さまが強い胸痛を訴えることから病名を推測した上で、診断を確定させるために心電図検査や血液検査を行います。
治療について
急性心筋梗塞であれば、閉塞した血管を速やかに再開通させる必要があります。具体的には、血栓を溶解させる薬剤を注射する血栓溶解療法、またはカテーテルを用いて詰まっている血管部位を拡張させる冠動脈形成術が行われます。これらの方法では改善が困難な場合は、心臓の開胸手術としてバイパス手術を行うこともあります。
心筋梗塞の発症後、ある程度時間が経過している場合は、薬物療法として、スタチン系薬剤や抗血小板薬などを使用します。また、再発予防のため、生活習慣の見直し(禁煙、肥満の解消 等)、生活習慣病の治療も行います。
心不全
心不全とは
心臓は血液を各機関へと送る際、ポンプのように収縮していますが、その機能が低下している状態を心不全といいます。心臓がしっかり収縮することができなければ、血液を十分に送ることができず、その結果、組織に血液が溜まり、「うっ血」という状態が起こります。
このような心機能が低下する状態は、心筋梗塞、不整脈、弁膜症、高血圧、心筋炎などの心疾患によって引き起こされることが大半ですが、なかでも急性心筋梗塞がきっかけとなることが多いです。
心不全は急性心不全と慢性心不全に分けられます。心機能が急激に低下するのが急性心不全で、激しい呼吸困難と咳、泡状の痰(色がピンクになることも)などがみられます。慢性心不全では、体(すねなど足の部分 等)にむくみ、全身の倦怠感、息切れ、体重増加、易疲労感などの症状が現れます。どちらのタイプであったとしても、病状の進行具合によって現れる症状は変わります。
検査について
心不全が疑われる場合、胸部レントゲン撮影、心電図、心臓超音波検査、血液検査などを行います。また、急性心不全の患者さまには、速やかな初期対応が求められるため、診断がついたと同時に治療が開始されます。
治療について
急性心不全の患者さまは、入院して安静な状態を保つ必要があります。入院中は、酸素吸入のほか、利尿薬(血液の量を減らす効果がある)、血管拡張薬、強心薬などの薬物療法も用いられます。慢性心不全の患者さまも安静に努め、利尿薬や降圧薬などによる薬物療法や、塩分の摂取量を減らすための食事療法を行います。
不整脈
不整脈とは
一定のリズムで繰り返される心臓の拍動(心筋の定期的な収縮)が、何らかの原因によって、不規則に拍動している(期外収縮)、速すぎる(頻脈)、遅すぎる(徐脈)と診断された状態を不整脈といいます。
これらの症状は、心疾患の一症状としてみられることもありますが、加齢や疲労、睡眠不足、体質的なことで起こることもあります。なお、人間の心臓は1日約10万回拍動しているので、その間に一時的な不整脈になることは少なくありません。つまり、拍動が不自然であると診断されたからといって、何も問題がなかったということはよくあります。しかし可能性として、狭心症・心筋梗塞、心不全などの心臓病で現れることもあるということを、念頭に置く必要があります。
不整脈の種類
前述のように3つのタイプ(期外収縮、頻脈、徐脈)に分類されます。期外収縮では、脈が飛ぶような不規則な間隔になるほか、胸がつかえるなどの症状がみられる状態になります。ちなみにこのタイプの多くは、心配のいらない不整脈と言われています。
頻脈とは、脈拍が異常に早くなっている状態です。数値としては、1分間に100回以上の拍動がある、もしくは心臓の電気信号が1分間に250回以上送られている場合(細動)と定義されています。主に胸痛や動悸、不快感がみられるほか、失神が起きることもあります。頻脈性不整脈の一種である心房細動は脳梗塞の原因にもなりやすく、また、心室細動は意識を失いやすくなります。さらに、脳、腎臓、肝臓等の臓器に血液が送られにくい状態になるので、心臓が停止し、突然死に至ることもあれば、心臓の活動を過剰にさせることで、負担がかかりやすくなり、心不全に至るケースもあります。また心疾患以外でも、貧血、更年期障害、甲状腺機能亢進症などの症状の一つとして起こることもあります。
徐脈は、拍動が1分間に50回未満と判定された場合をいいます。主に、息切れ、易疲労感、めまいなどの症状がみられるほか、失神が起きることもあります。なお心拍数が少なくなれば、心臓から送られる血液の量も少なくなるので、心不全が起きやすい状態にもなります。
検査について
不整脈を診断する場合は、心電図検査(12誘導心電図、24時間ホルター心電図、運動負荷心電図)をはじめ、胸部X線撮影や心臓超音波検査等の画像検査のほか、何らかの病気発症の可能性を調べるために血液検査などを行っていきます。
治療について
原因疾患が特定していれば、それに対する治療を行っていきます。なお不整脈でみられる症状を軽減させたいという場合は、抗不整脈薬などによる薬物療法を用います。薬物療法で改善が困難であれば、徐脈の患者さまにはペースメーカー、頻脈の患者さまには電気的除細動やカテーテルアブレーション治療が選択されることもあります。

